生成AIにも「不気味の谷」があるって知っていますか?
2025.07.07
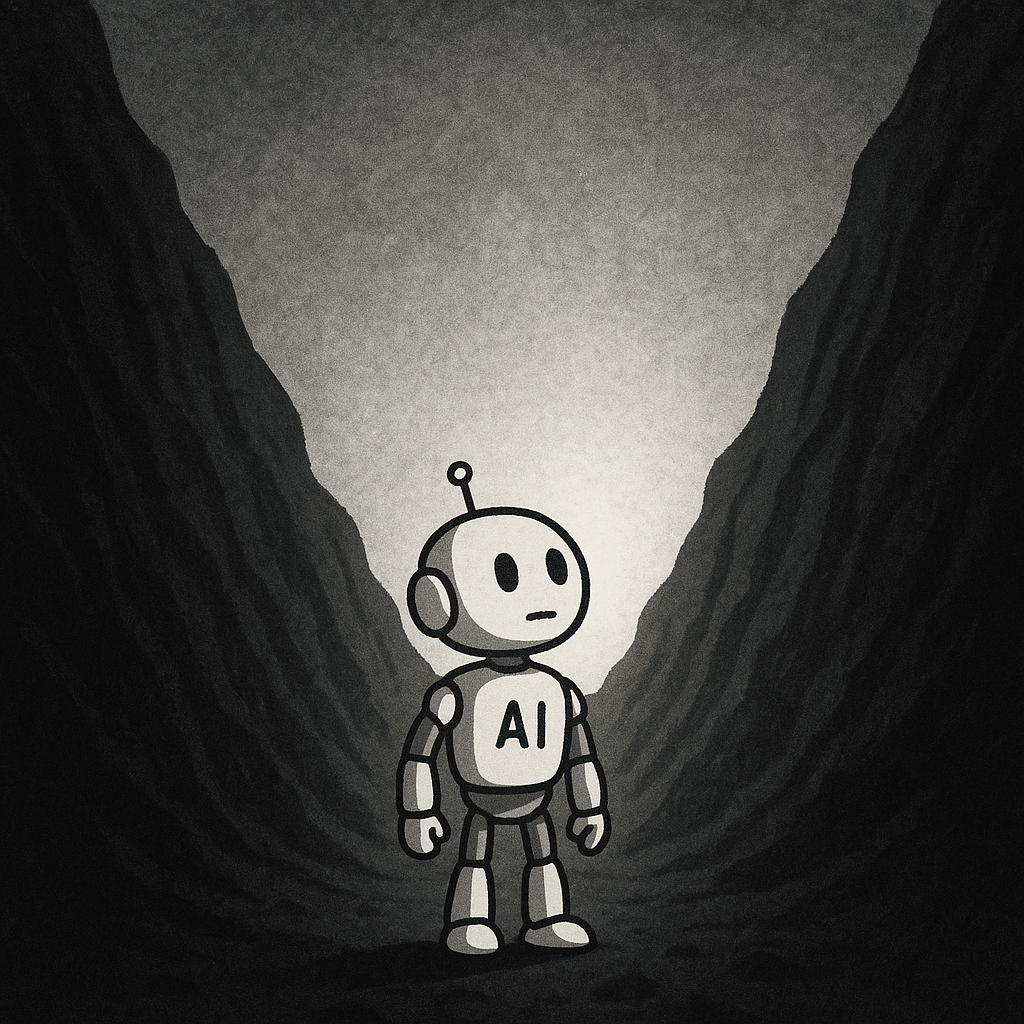
こんにちは。
AIがどんどん人間に似てきて、違いが見えにくくなってきました。
それを面白いと感じるか、怖いと感じるか。
たぶん、時代はどちらにも傾き得るんですよね。エンパワテックの廣重です。
今回はちょっと心理学寄りの話題を。
それは「不気味の谷(Uncanny Valley)」という現象と、生成AIの関係についてです。
「不気味の谷」って何?
まずはこの言葉の意味から。
「不気味の谷」とは、人間に似ているロボットや映像キャラクターに対して、あるレベルを超えると不快感を覚えるという心理現象のことです。
1970年にロボット工学者・森政弘氏によって提唱されました。
たとえば:
・ゆるキャラ → かわいい
・人型ロボ → おもしろい
・超リアルな人型ロボ → なんか怖い…
この「かわいい → 好感 → …一気に不気味」になる感情の急降下ゾーンが、「不気味の谷」なんです。
そして今、それが「言葉」の世界に現れている
昔は「見た目」の話でしたが、今は生成AIの言葉やふるまいにも同じような谷が現れています。
たとえば:
・すごく自然な文章なのに、なぜか読んでいて引っかかる
・共感してくれる風だけど、なんだかうわべだけな感じがする
・逆に自然すぎて、「本当にAIなの?」と不安になる
この感覚こそが、生成AIの「不気味の谷」です。
AIに「心」がないと、わかっているはずなのに…
私たちは、AIが「ただのプログラム」であることを知っています。
でも、会話の文脈や感情表現があまりに自然でリアルだと、つい「人間らしさ」を感じてしまう。
でも…
完全には通じ合えない。
ここで、「ああ、やっぱり機械なんだ…」というズレを体験します。
その瞬間に、人は「怖い」「不気味」と感じてしまうのです。
これは進化の証でもある
ある意味では、不気味の谷に入るということは、
人間にかなり近づいてきた証拠とも言えます。
・表現が雑だった時代には起きなかった違和感
・本物に似てきたからこそ生まれるギャップ
そう考えると、「AIの不気味さ」は、技術の進歩そのものなんです。
じゃあ、どう付き合うべき?
不気味に感じることを「怖いから使わない」と決めてしまうのは、少しもったいないかもしれません。
むしろ大切なのは、
「どこからが任せられて、どこからが人間の判断領域か」を、自分なりに意識すること。
AIがどれだけ進化しても、
「心を込める」のは、私たち自身だからです。
最後に
AIの会話にちょっとした違和感を覚えるのは、
あなたが敏感で、繊細な感受性を持っている証かもしれません。
けれど、だからこそ、
AIという存在に「気づき」や「問い」を重ねていく力が、私たちにはあるのだと思います。
その違和感の先にあるのは、
きっと、AIと人間が本当にわかり合える未来なのかもしれません。




 お問い合わせ
お問い合わせ