AIによって仕事が速くなる未来──その先に人間は考えなくなるのか?
2025.07.02
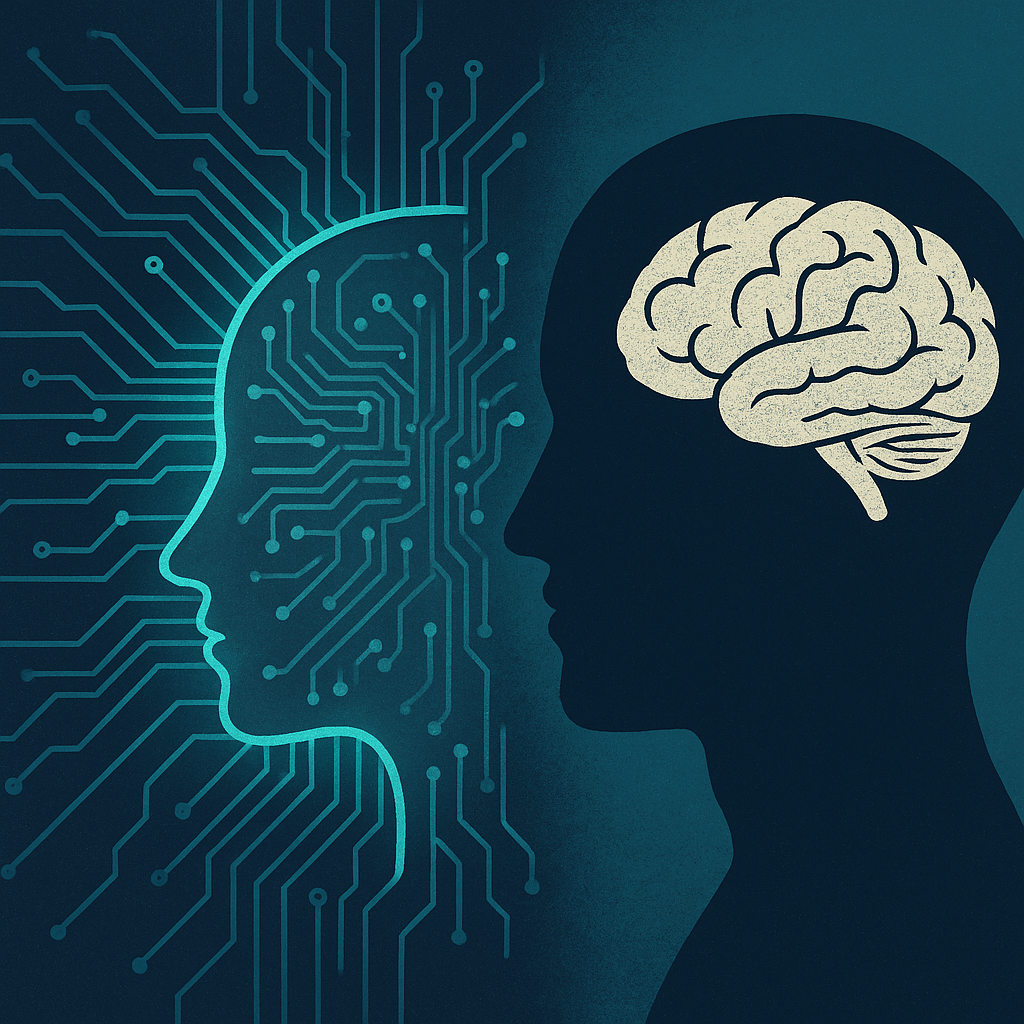
こんにちは。
AIと雑談しながら、未来のことを本気で考えてます。エンパワテックの廣重です。
文章の要約、情報収集、企画書の叩き台づくり。
かつて何時間もかけていた作業が、いまや数秒〜数分で完了してしまう。
そんな体験を、すでに日常の中で感じている方も多いと思います。
でも、ふと考えるのです。
このスピードの先にあるのは、
私たち人間が「考えなくなる未来」なのか?
それとも「より深く考える未来」なのか?
AIは、考える前の準備を代行してくれる
今のAIは、とても優秀な「助走担当」です。
・調べる
・並べる
・整える
・まとめる
こうした思考の前段階を、ものすごい速さでこなしてくれます。
だからこそ、時間が浮きます。
でもその時間、私たちは何に使っているでしょうか?
「考えなくなる未来」は、すぐそこにあるかもしれない
たとえば、、
・プレゼンの冒頭文をAIに書かせて、そのまま出す。
・アイデアを10個出させて、「一番それっぽいもの」を選ぶ。
・会議の要点だけを要約で読み、議事録は見ない。
そんな使い方が日常になると、
私たちは「考える筋力」をゆっくりと失っていく、そんな気がします。
AIが考えてくれるから、自分はもう考えなくていい。
それは便利ですが、同時にちょっと怖い。
でも、深く考える人はもっと深くなる
一方で、AIの出す答えに対して
・「なぜこの結論になったんだろう?」と問いを立てる人
・自分の仮説とAIの仮説を比べて、精度を確かめる人
・AIの答えを、出発点として再解釈する人
こういう人たちは、AIを「答え」ではなく「刺激」として使っている。
彼らにとってAIは、考えることを奪う存在ではなく、考えるための道具になっています。
結局、未来はどちらにもなり得る
便利さに委ねて、思考を手放すか。
便利さを踏み台にして、思考を深めるか。
AIが進化すればするほど、
人間の「問いの質」と「考える姿勢」が問われてくる。
最後に
AIがどれだけ進化しても、
「なぜそれを考えるのか」
「どの答えを選ぶのか」
を決めるのは、まだ人間です。
スピードのその先に、
深さがあるのか、空白があるのか。
それは、AIの性能ではなく、私たちの在り方が決めることなのかもしれません。




 お問い合わせ
お問い合わせ